「うちは財産も少ないし、遺言なんていらないのでは?」
そんなふうにお考えの方も多いかもしれません。
しかし、遺言は“争続(そうぞく)”を防ぎ、自分の意思を確実に遺すための大切な手段です。
特に「おひとり様」「お子さまのいないご夫婦」「内縁関係」など、家族構成が多様化する今、遺言の有無が家族関係や財産処理に大きな影響を与える時代になっています。
この記事では、遺言の中でも特に多くの方が利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、その違いや作成時のポイントを行政書士の立場からわかりやすく解説します。
遺言とは?基本をおさらい
遺言とは、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や意思を記した法的効力のある最終メッセージです。
遺言があることで、相続人間のトラブルを防ぎ、自分の意志に基づいた財産の分配が可能になります。
代表的な遺言の種類には、次の2つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
それぞれの特徴と違いを詳しく見ていきましょう。
1. 自筆証書遺言とは
ご本人が全文を自筆で作成する遺言です。
費用がかからず手軽に始められる一方、いくつかの注意点もあります。
【メリット】
- 手書きで簡単に作成できる
- 費用がかからない(公証役場の手数料不要)
- 内容を誰にも知られずに作れる
【デメリット】
- 書き間違いや形式不備で無効になるリスクがある
- 発見されない、または破棄される可能性がある
- 相続開始後に家庭裁判所の「検認手続き」が必要
- 字が読めない、高齢で筆記困難な場合には不向き
📌2020年7月〜「法務局による保管制度」がスタート
これにより、法務局に遺言を預けておくことで、
- 紛失・改ざんの心配なし
- 家庭裁判所の検認が不要 といったメリットが増えました。
2. 公正証書遺言とは
公証人が本人の意思を確認しながら、公正証書として作成する遺言です。
証人2名の立ち合いが必要ですが、最も確実で安全な方法と言えます。
【メリット】
- 法的に無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
【デメリット】
- 費用がかかる(公証人手数料・専門家への報酬)
- 証人が2名必要(専門家に依頼可能)
- 手続きがやや煩雑(準備に時間がかかることも)
💰費用の目安
財産額や内容によって異なりますが、
公証人の手数料は1万円〜10万円程度、
行政書士等のサポート費用は別途かかります。
⚖️3. こんな方には公正証書遺言がおすすめ
以下のようなケースでは、公正証書遺言で確実な準備をおすすめします。
- 相続人間の仲が悪い、または疎遠
- 財産の分け方に偏りがある(例:長男に全てを遺したい)
- 法定相続人以外に財産を残したい(内縁の配偶者、友人、団体など)
- 認知症や病気の不安がある(意思能力がしっかりしている今がチャンス)
- 高齢や身体の不自由で自筆が難しい
💡4. 自筆 or 公正証書?迷ったらプロに相談を!
遺言は一度書けば終わりではなく、ライフスタイルや家族構成に応じて見直すことも大切です。
行政書士などの専門家に相談すれば、次のようなサポートが受けられます。
- 法的に有効な遺言の作成支援
- 財産目録の作成・確認
- 相続トラブルを避けるアドバイス
- 見守り契約や死後事務委任との連携提案
遺言は「自分のため」ではなく、「残される人のため」の準備でもあります。
🌸まとめ|大切な想いを“確実に遺す”ために
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。
大切なのは、ご自身の状況に合った方法で、確実に「想い」と「財産」を遺す準備をしておくことです。
特に高齢化・おひとり様・おふたり様世帯の増加により、“遺言がないことで相続が混乱する”事例が増えています。
だからこそ、早めの準備がトラブルを防ぎ、ご自身とご家族の安心につながります。
当事務所では、遺言作成のご相談はもちろん、家族信託・死後事務委任・見守り契約など、ワンストップで終活全般のサポートが可能です。
まずはお気軽に、無料相談やセミナーをご活用ください。
お問合せ⇒やまの行政書士事務所
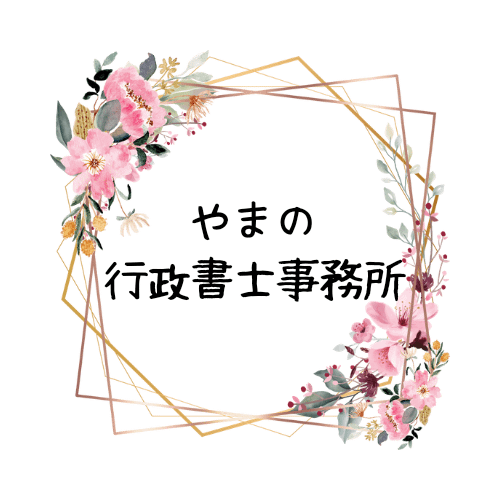
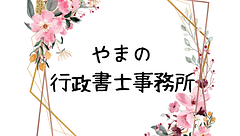
コメント