少子高齢化や未婚化が進む現代、身寄りのない「おひとり様」や、お子さまがいない「おふたり様」が増えています。
そのような中、「もしもの時、誰に頼ればいいのか」「自分が亡くなった後の手続きはどうなるのか」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士の視点から、おひとり様・おふたり様にこそ知っておいていただきたい「終活」の具体的な手段をご紹介します。
特に重要なのが「遺言」「家族信託」「死後事務委任契約」など、将来のトラブルを未然に防ぎ、自分の意思を実現するための仕組みです。
🔹1. おひとり様・おふたり様の終活で大切な3つのこと
終活は「人生の締めくくり」の準備をする行動ですが、単なる“終わり”ではありません。自分の意思を反映し、大切な人や財産を守る“未来への贈り物”でもあります。
おひとり様・おふたり様が特に注意すべきポイントは以下の3つです。
- ✅ 亡くなった後の手続きをお願いできる人がいない
- ✅ 財産の分け方を明確にしないと争いが起こりやすい
- ✅ 病気や認知症になったときの判断能力の低下リスク
これらの問題に備えるために、法的な仕組みを上手に活用することがとても大切です。
🔹2. 自分の思いを遺す「遺言書」の種類と使い方
「うちは財産が少ないから遺言なんていらない」と思っていませんか?
実は相続トラブルは“もめごとになるほどの財産がない家庭”でも多く起こっています。
▷ 自筆証書遺言
- 自分で全文を書く手軽な方法
- 2020年から「法務局での保管制度」も開始
- 書式ミスによる無効に注意
▷ 公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成
- 専門家のチェックでミスなし
- 安心・確実に遺志を残せるので高齢者には特におすすめ
遺言書には**遺贈(特定の人や団体への贈与)**などの希望も記載できます。おひとり様が信頼できる友人や支援団体に遺産を託したい場合にも有効です。
🔹3. 認知症などに備える「家族信託」の活用法
近年注目されている「家族信託」は、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託し、管理や処分を任せる制度です。
- 認知症になっても財産の凍結を防げる
- 成年後見制度より柔軟に財産を扱える
- 相続ではなく「贈与」に近い自由度がある
例えば「マンションの管理は甥に任せたい」「老後の生活費は子どもが管理してほしい」など、個別のニーズに合わせて設計できる点が魅力です。
🔹4. 死後の不安を解消する「死後事務委任契約」
自分の死後に必要な手続きを、生前に信頼できる人と契約で託しておく制度です。
行政書士が受任者となることも可能で、以下のようなことを代行できます。
- 病院や施設の退所手続き
- 火葬・納骨・永代供養
- 公共料金や住民票の抹消
- 遺品整理や家の処分
特に身寄りのない方やおひとり様には心強い備えになります。
🔹5. 終活の入り口は「見守り契約」や「エンディングノート」
まだ元気なうちから信頼関係を築いていくのが、終活の第一歩です。
▷ 見守り契約
- 行政書士などが定期的に連絡・訪問
- 異変の早期発見や安心感につながる
- 任意後見契約や死後事務委任へのステップにも
▷ エンディングノート
- 自由形式で人生の希望を記録
- 医療・介護・葬儀の希望、財産のありか、連絡先など
- 遺言書と併用することで「思い」と「法的効力」を補完
🔹6. ペットを守る「ペット信託」も注目の終活対策
おひとり様・おふたり様にとって、ペットは家族そのもの。
自分が亡くなった後も安心して暮らせるよう、信託でペットの世話や費用を第三者に託す仕組みが「ペット信託」です。
- 誰に託すか、どう飼育してもらうか明記
- 飼育費用を信託財産として準備
- 弁護士や行政書士がサポート
🌸まとめ|自分らしい最期のために、今できる備えを
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちにこそ備えるのが終活の基本です。
おひとり様・おふたり様だからこそ、“頼れる人”と“仕組み”を先に用意しておくことが安心に繋がります。
行政書士は、法的な手続きだけでなく、心に寄り添う終活のパートナーです。
見守り契約から始めて、遺言・家族信託・死後事務委任など、あなただけの終活設計を一緒に考えてみませんか?
お問合せ⇒やまの行政書士事務所
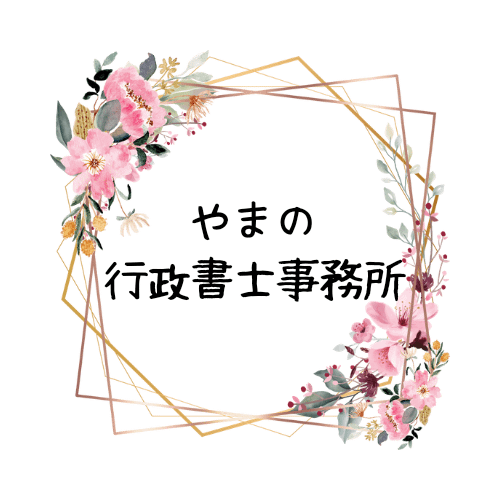
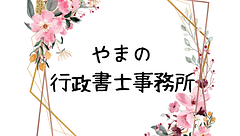
コメント